私の体験:親の老いを感じることが増えた
私は長女ということもあり、両親にとても頼られています。病院への付き添いや、各種手続き、ちょっとした困りごとまで「とりあえず私に頼む」スタイル。頼られるのは嬉しい反面、自分の生活や仕事の予定を削らなければならないことも多く、次第に心にモヤモヤがたまっていきました。
「子どもだから親の面倒を見て当たり前」?
親のことは大切。でも、どこかで「全部私がやらなきゃ」という空気があって、それがとても重たく感じていました。妹は「お姉ちゃんがしっかりしてるから大丈夫でしょ?」というスタンス、娘も「ばあばのことお願いね」と言うばかり。家族の中で“頼れる人”として固定されてしまった感覚がありました。
「私にも生活があるのに」「なんで全部私なの?」とイライラが募り、自分の親なのに優しくできない自分にも自己嫌悪…という負のループに陥っていたんです。
救急搬送された夜、全員がハッとした
ある日、母の通院の付き添いが連日続いていた頃、仕事も忙しく、有休も限界。
どうやら私の体力も気力も限界を超えていたようです。疲れがピークに達した私自身が急性胃腸炎で倒れてしまいました。うずくまり動けなくなった私は救急車で搬送される事態に。
📌 専門家の見解:介護とストレスの関係
同居の主な介護者について、日常生活での悩みやストレスの有無をみると、「ある」60.8%、「ない」22.7%となっている。性別にみると、「ある」は男54.2%、女63.7%で女が高くなっている。
― 出典:厚生労働省・同居の主な介護者の悩みやストレスの状況
その姿を見て、両親も妹も、そして娘も「これはマズい」とようやく気づいたようです。「お姉ちゃんに任せすぎた」「お母さんに頼りすぎた」と反省の言葉が口をついて出ました。
まさか自分が倒れるまで気づいてもらえないなんて…
いえ、私自身も気づいてなので仕方ない面もありますが、きっかけとしては充分でした。
少しずつ見えてきた「遠慮」と「役割分担」
今では、母も「できることは自分でやる」と言うようになりました。通院の日も自分で予約を取ってタクシーを手配し、妹にもこまめに連絡を取ってくれるように。
私はというと、体調を整えることを最優先に。「無理しないで」と言われても、「無理しないと回らないんだよ」と思っていた私でしたが、倒れてみて本当に無理していたことに気づいたのです。
親が年を重ねるように、私たちも変化しています。だからこそ、お互いが「できること」と「できないこと」を共有して、歩み寄ることが大切だと思うようになりました。

介護と人生、どちらも大切にするバランス
「親の介護にすべてを捧げる」か「自分の人生を優先するか」ではなく、バランスが必要だと痛感しています。
たとえば…
- 母の付き添いは「月○回まで」と決める
- 妹や他の家族に「頼る」勇気を持つ
- ケアマネージャーや福祉サービスに相談する
一人で全部抱え込まなくていい。そのことに気づけただけでも、大きな一歩でした。
まとめ|遠慮と感謝、どちらも大切に
50代は、親も自分も“人生の後半戦”に差し掛かっている時期。だからこそ、ただ支えるだけでなく「一緒に良い関係を築くこと」が必要なのだと思います。
大切なのは、距離のとり方。頼られることも嬉しいけれど、時には甘えさせてもらうこと。すべてを抱えるのではなく、信頼して任せること。
そんな小さな変化の積み重ねが、親との関係をあたたかいものにしてくれるのだと思います。
関連記事
🌿 あわせて読みたい関連記事
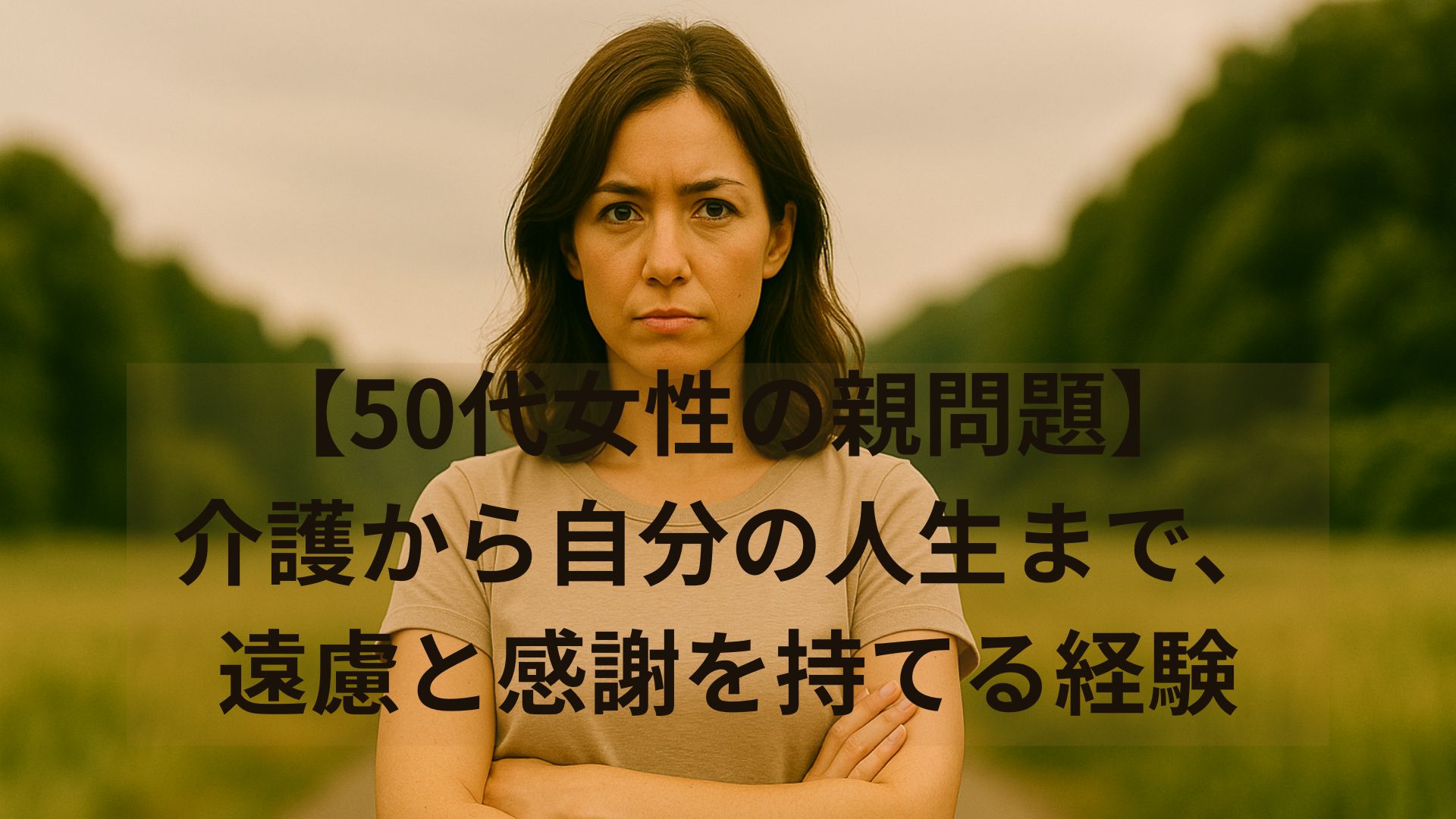


コメント